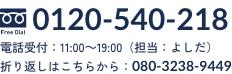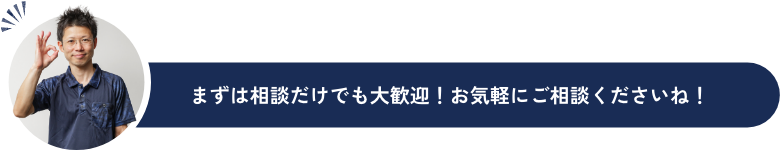浴室の壁等に発生するピンク色のヌメリ汚れは「赤カビ」とも呼ばれています。正確には、汚れの正体は「ロドトルラ」という酵母菌やバクテリアの一種です。
一般的によく目にするのが、シャンプーやボディーソープの底、排水口周り、ゴムパッキン、石鹸受け等でピンク色になっているところを見たことがあると思います。こちらがロドトルラです。中性洗剤もしくはアルカリ性洗剤を使用して落として下さい。
ロドトルラの発生場所は、カビとよく似ていますが、大きく違う点がは菌の増えるスピード、繁殖力の強さ、発生場所の広さが挙げられます。高温多湿を好み、洗剤の残り、石鹸カス、皮脂、水分、汚れ等を栄養分として繁殖します。それらの条件が揃ったお風呂は特にロドトルラの発生を助長してしまいます。
ロドトルラは繁殖スピードがとても早く、空気中にも存在する菌になるので、こまめな掃除をしても発生源を断つのは難しく、すぐにできてしまうのが難点ですが、カビのような根があるわけではないので、こするだけで簡単に落とすことができます。ピンク汚れは黒カビが生えやすくなる原因でもあるので、見つけたら早めに汚れを取り除きましょう。
ピンク汚れを効果的に落とすために掃除にひと手間加えるだけで、繁殖しやすい環境を阻止できます。簡単に且つ効果的にピンク汚れを落とす為のポイントを紹介します。
ピンク汚れはブラシ等でこすって洗い流せばすぐに除去できるのですが、綺麗になったように見えているだけで実は菌がまだ残ってしまっていることが多いです。酵母菌自体が死滅しているわけではないので、掃除をしても数日でまた同じ場所に発生してしまいます。ピンク汚れを完全に除去するには、菌を確実に死滅させる必要があります。裂傷等の消毒にもよく使われる消毒用エタノールは、殺菌力が強く、ピンク汚れの菌にもとても効果的です。また、掃除をしても水気や湿気が残っていると再び繁殖してしまうので、汚れが落ちたらしっかりと乾燥させるのもポイントです。ピンク汚れでお困りの方は、是非お試しください。塩素系漂白剤でもピンク汚れの死滅に効果がありますが、体にあまり良くないので極力使わない方法をお伝えさせていただきました。
使用頻度の高い水回りの水分や湿気に気を配ることは難しいですが、水分をできる限り残さないことがピンク汚れの発生を抑えるうえで大切となります。
浴室内のピンク汚れを予防出来たら掃除の負担が減り、水回りの清潔が保てます。ピンク汚れを発生させない為に水分を除去する以外にもできる対策がいくつかあるので紹介します。
ピンク汚れの予防方法1つ目は、熱湯をかけることです。ロドトルラは温度、湿度、栄養分の3つが揃うことで繁殖します。栄養分になる皮脂、石鹸カス、洗剤残り等を熱めのシャワーでしっかり流しましょう。壁や床だけでなく、シャンプーのボトル裏にも洗剤が残っていると、水分と混ざり合い繫殖スピードが早まってしまいます。
ピンク汚れの予防方法2つ目は、冷水シャワーを全体的にかけ、温度を下げることです。高温はロドトルラだけでなく、カビが好む繁殖条件でもあるので、温度を下げることはピンク汚れとカビの予防をするうえで重要なポイントです。
ピンク汚れの予防方法3つ目は、換気をすることです。ロドトルラは水分さえあれば繁殖していきます。入浴後1~2時間程度、しっかり換気扇をまわし乾燥させることで、水分が取り除かれピンク汚れやカビの繁殖を抑えられます。掃除の手間を減らし、湿気による浴室の腐食も防げるので清潔を長持ちさせられます。
ピンク汚れの予防方法4つ目は、水はけをよくすることです。浴室であれば、ボトル類や小物類の水はけに注意しましょう。水分が溜まりやすく、ピンク汚れが発生しやすい場所です。床に面している部分は特に見落としてしまいがちなので、入浴後に椅子を浴室に立てかけて乾かすのもお勧めです。ボトル類は水はけのよいラックにしまったり、クリップタイプで吊るして収納したりすることで万遍なく水分が切れます。
ピンク汚れは水分が少しでも残っている限り繁殖してしまいます。油断すると繁殖が繰り返されカビの原因にもなってしまいます。浴室内やピンク汚れが気になる場所の風通しを良くして、湿気を取り除きましょう。普段からのメンテナンスで実は落ち切っていないこともあり、気付けば頑固な黒ずみやカビが蓄積してしまうこともあります。掃除と予防の方法を覚え、必要であればプロへの掃除依頼も活用しながら、ピンク汚れの発生を防ぎましょう。